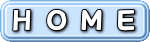


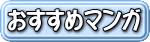





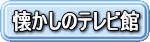
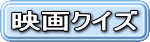
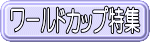





|
|
| 栗色の髪のジョナサン |
初めてあの人に会ったのは、ある春の日のうららかな午後だった。
私はミネアポリスの母の元を離れ、心機一転してこの小さな町で教師の仕事を始めてから数年が経っていた。
私の教える学校の建物は相当年季が入っていて、雨漏りや何かで痛み始めていた。その建物の補修にやってきたのが、彼ジョナサン・ガーベイだった。
初めて彼を見た時はその雲をつくような大男ぶりに正直なところ微かな恐れさえ抱いてしまった。
「こんにちは、先生。今日から、授業後に補修にかかりたいんですが」
彼は栗色のちょっともじゃもじゃの髪をして、やはり顎を覆うもじゃもじゃの髭を生やしていた。体は背が高いだけでなく、胸板の厚い相当がっしりした体格だった。しかし、よくよく見てみると眼が優しい。その大きな体からはちょっと想像がつかないほど、茶目っ気さえ感じさせるような優しくて可愛い眼だった。
その日から、天気の良い日には毎日彼はやってくるようになった。
「こんにちは、先生」
彼はいつも帽子をとって私に挨拶してくれた。私が教室に残って答案の採点をしていると、彼が鼻歌を歌いながら金槌をトントン叩いているのが聞こえる。いつの間にかその金槌の音が私には快い音楽のように聞こえてくるようになった。
ある日、私はお茶と前の日に焼いたクッキーを持っていって、彼に休憩を勧めた。
「こりゃあ、すみません」
彼はちょこんと会釈して窮屈そうに学校の椅子に座った。なるほど、彼の巨体では学校の椅子も窮屈だろう。
「いつもご苦労様です」
「いやあ、これも仕事ですから。先生こそ、うるさいでしょう。すみませんね」
「でも、これも私の仕事ですから」
私たちはクスリと笑いあった。
学校の鍵を閉めるために、私は修理の間学校に残らねばならなくて、最初はそれが憂鬱だった。修理の音が響くところで、答案の採点や翌日の授業の準備など出来るものではない。
事実、最初のうちはなかなか集中出来なくて困ったのだったが、彼の修理は静かとは言えないにしても、独特のリズミカルな音で騒音とは感じないのが不思議だった。
「それで、森の中でクマに出逢った時ほどびっくりしたことはなかったですよ」
彼はお茶を飲みながら、自分の武勇伝を語った。
「実のところ、銃を構える余裕もなかった」
「それでどうなさったの」
「クマに向かって両手を振り回して、ワーワーわめきましたね。するとクマの方がきょとんとしてね、首をかしげるように私を見てのそのそ去っていきましたよ。この風貌だから、仲間と思われたかな」
彼はもじゃもじゃのあごひげをなでた。
私は思わず声を立てて笑ってしまった。
「御免なさい。あんまり面白くて・・・」
彼はニコニコ私を見ていた。
学校の修理は2週間ほどで終わった。雨漏りも風が吹き抜けることもなく快適な教室が戻ってきた。
しかし、それは彼との別れを意味してもいた。
日曜日の教会で牧師さんの話を聞いたあと、後ろから声をかけられた。
「先生」
ジョナサン・ガーベイ!まあ、何とバッチリスーツを着こなして恰好良いこと。
「久しぶりです。教室はどうですか。不具合はありませんか」
「ええ、とても快適になりました。あなたのおかげですわ」
「それは良かった」
彼はモジモジと髭をいじくっていた。
「その、今日は天気が良いですね」
「ええ、本当に。気持ちの良い日です」
「馬車で来ているんですが、その〜、どうですか、ちょっとピクニック気分で遠乗りしてみるっていうのは」
私はちょっと驚いた。あのジョナサン・ガーベイが私を誘っている?いえ、深い意味はないのかもしれないけれど。
「いや、お忙しいなら良いんです」
彼は慌てて言った。ちょっと顔が赤かった。あの大男がこんなに純真になれるなんて・・・私の胸が温かくなった。
「いいえ。こんなに良い日ですもの。遠乗りしてみたいわ」
ジョナサンと私が恋に落ちるのに長い時間は必要なかった。大きな体をしていながら、子供のような純真さを持って恥ずかしがり屋のところさえある彼が私にはいとおしかった。
彼は理想主義者でもあった。いつかもっと西に行くことが夢だとも語った。
「小さくても良い。自分の農場を持って自分の城を築きたい。そのためには今が正念場でね。何でもやってお金を稼いでいるわけですよ」
「まあ、立派な夢ですね」
「ミネソタの大草原あたりが良い。土地も肥えてるし、作物の育ちも期待出来る。でも、農民の生活なんて先生には想像出来ないでしょうね。来る日も来る日も畑を耕して、真っ黒になって働いて、それなのに天候次第ではすべてが水の泡になる可能性もあるんだから」
「でも、国を支えているのはそういう人たちですわ。そういう人たちの作ってくれる作物なしで、私たち暮らしていけないもの」
「そう思いますか?」
ジョナサンの目はキラキラ輝いていた。
ジョナサンと私の逢う頻度はますます高まっていった。私の心の中にこれで良いんだろうか?という気持ちが巣くっていたが、自分の熱情には勝てない。
私の誕生日を祝う夜の食事に招待した夜、ジョナサンは久しぶりにスーツを着てやってきた。
「アリス、お誕生日おめでとう」
ジョナサンは大きな花束を渡してくれた。それらは野性の花だったが、なんとあでやかで芳しかったことだろう。
「それにプレゼント」
ジョナサンの渡してくれた箱を開けると綺麗なカメオのブローチが出てきた。
「まあ、ジョナサン、こんな豪華なもの」
「気に入ってもらえるかどうかわからなかったんだが・・・」
「素敵だわ。付けるのが勿体ないくらい」
ジョナサンはブローチを手に取ると私の襟元に付けてくれた。
「よく似合うよ。アリス」
私の心づくしの手料理を食べて私たちは至極満ち足りた気分になっていた。
今までの誕生日は一人で迎えることが多かった。母のところに帰るのは遠くて大変だったし、町の人々と交流はあっても一緒に誕生日を祝ってくれるほどの人はいない。
ゆらゆら揺れるランプの灯に照らされていつにも増してジョナサンはハンサムに見えた。
「アリス」
唐突にジョナサンが声をかけてきた。ちょっと声が震えているようだった。
「実はもう一つプレゼントがあるんだ」
「まあ、ジョナサン。もらいすぎだわ」
ジョナサンは、ポケットから小さな箱を取り出して、テーブルを回って私の元にやってきた。綺麗な包装紙のかかった箱にはピンクのリボンがかかっていた。
私は箱を受け取ると包装紙を破かないように静かに箱を開けた。
私が中のものを見て驚きの声を挙げたその時にジョナサンは私の前でひざまずいた。
「アリス。どうか、結婚して欲しい」
私は箱の中の指輪とジョナサンを交互に見た。指輪は美しかった。コツコツとお金を貯めてきたジョナサンには相当な散財だったに違いない。そして、目の前のジョナサンのこれほど真剣な表情は今までに見たことがなかった。
「前にも言ったね。きっと僕は農場を持ってみせる。君を幸せにする。苦労はかけない」
ジョナサンの優しい瞳、大きな手。たくましい腕。その全てに自分をゆだねてしまいたいという気持ちが私の中に湧き起こった。イエス、ただイエスと言えば良いのだ。そうすれば彼と私には輝かしい未来が待っている。アリスとジョナサン・ガーベイ。きっと私たちは幸せな夫婦になる。そう、結婚して素敵な夫婦に・・・。結婚・・・。
「私・・・」
ジョナサンは顔を輝かして待っている。そう、ただイエスとさえ言えば。
「でも、私・・・」
自分でも思わぬ言葉が口をついて出た。
途端にジョナサンの顔が曇った。
「あの・・・早すぎると思うの。知り合ってまだ半年だし。それに・・・」
「僕には十分過ぎる時間だった。僕は君を知ってこの人しかいない、と思った」
「ええ・・・でも、もう少しお互いを知ってからでも良いのじゃないかしら」
ジョナサンは立ち上がった。
「これ以上、何を知る?僕は僕の全てを君に話して、見せてきた。これ以上、知るところはないよ」
私たちの間に重い沈黙が流れた。
「でも、あなた西に行きたいんでしょう。生活ががらりと変わるし」
「そうだ。確かにそれは君には大変なことだと思う。でも、僕が付いているし、全力で君を守る」
ジョナサンが再び熱いまなざしを向けてきた。
「考える時間が必要だというなら待つよ。でも、もし僕を愛してないならそう言って欲しい」
愛している?そう、私は彼を愛している。でも、そう言ってしまえば全ては結婚へと流れていく。
「私・・・わからないの」
またもや、思わぬ言葉が口をついて出た。
「わからないって?自分の気持ちがわからないのか?新生活への不安なら色々調べて、準備を整えて不安を解消していくことも出来る。でも、自分の気持ちがわからないって・・・。僕たちはもう十分に自分の気持ちをコントロール出来る大人のはずだ。君もそのつもりでつきあってくれているんだと思ってた」
「御免なさい、ジョナサン・・・」
「今日はごちそうさま。遅くなるから失礼するよ」
ジョナサンは私の見送りも受けないで足早に立ち去った。
残された私は、彼のくれた指輪を見つめた。前にもらった指輪とどことなく似ている。結婚に幸せの夢を描いていた頃の思い出が私の脳裏に思い浮かぶ。ああ、ハロルド・・・確かに最初は幸せだった・・・けれど・・・けれど。
結婚して2人で人生を切り開くのだと言えば聞こえは良い。でも、現実はそう簡単に進まないことも多い。結婚は生活なのだ。愛だけでは成り立たない。ハロルドのことだって、どんなに愛したか。でもあの人は変わっていった。ジョナサンがそうならないという保証がどこにあるだろう。私が我慢出来るという保証がどこにあるだろう。
私は指輪を握りしめたまま、テーブルクロスの上にひれ伏してただ泣いた。
ジョナサンとはもう2週間逢っていない。エンゲージリングを返さねばと思いながらも、彼のところに出向く勇気が出なかった。彼の方からも何も言ってこない。
私は家と学校を往復するだけの日々を送った。ジョナサンと逢わない日々は、彼との楽しい時を知ってしまった今となっては余計に孤独感を増す。
学校の椅子が一つ壊れて修理が必要となった。
今度こそジョナサンに逢える。私は不思議なくらい気分が浮き立った。この前のことを謝ろう。でも、謝ってそれでもう一度答えを聞かれた場合どうすればいいのだろう。イエスと言えるだろうか、今の私に。
エンゲージリングを密かにバッグに忍ばせて、ジョナサンが放課後に修理に来るのを私は、喜びと恐れが半々の気持ちで待っていた。
「どうも先生、修理に来ました」
意外なことに現れたのは年輩のトニー・バレットだった。
「まあ・・・どうもすみません」
と社交辞令を並べながら私の胸はどきんどきんと警鐘を鳴らしていた。
「あの、ガーベイさんがいらっしゃるかと思ってたんですけれど」
思い切って切り出した私の言葉にトニーの返した言葉は意外なものだった。
「ああ、ガーベイはもう仕事はしないんで私が引き継いだんですよ。町を出て、西部に行くらしい」
私の胸は早鐘のように鳴りだした。もう何も考えられない。ただ、トニーが早く椅子の修理を終わってくれることをひたすら望んだ。
やっと学校に鍵をかけた私は、ほとんど駆けるようにジョナサンの家に飛んでいった。
ジョナサンの家はごった返っていた。多くの樽、缶詰、食料品、馬車の幌まで用意されていた。
私に気付いたジョナサンの顔に一瞬驚きがよぎったが、すぐに冷静な顔に戻った。
「やあ、アリス」
やあ、アリスですって?それだけなの?
「ジョナサン・ガーベイ、食料品屋でも始めるつもり?」
私は語気荒く言った。
「いいや、俺一人の食料さ。長旅になるかもしれないんでね」
小麦粉の大袋、とうもろこしの粉、コーヒー。これだけのものを詰め込んで、彼は行ってしまうと言うのだろうか。
「何も言わないで行くつもりだったんじゃないでしょう」
私は震える声で言った。
「そのつもりだったさ。君は俺を拒否したからね」
「ジョナサン・ガーベイ!」
ジョナサンは私の大声にちょっとびくっとしたようだった。
「いつ、私が拒否したと?」
「君はプロポーズを受け入れてくれなかったじゃないか」
「ええ、そうよ。でも拒否はしてないわ」
ジョナサンは、手にしていた荷物を下に降ろして私に近づいてきた。
「じゃあ、どうなんだ。アリス、結婚する気はあるのか」
ああ、どうしよう。こんな風に駆けつければこうなることはわかっていたのに。でも、来ずにはいられなかった・・・。
「私、これを・・・」
私はジョナサンのくれたエンゲージリングの入った箱を取り出した。
「返しに来たって言うのか。ハハ」
ジョナサンは自虐的に笑った。ああ、神様私はもう一度賭けてみることが出来るでしょうか。
「貴方は私を知らないわ」
「何を?君のことは知っている」
「例えば過去とか」
「過去に何かあったのか。君は君だろう。俺の望むのは過去じゃない。未来なんだ」
ジョナサンは私が掲げるように持っていた箱を取り上げた。
「一緒に生きていってくれる人が欲しかったんだ・・・」
彼は箱を開いて淋しそうにポツリと言った。
私はおもむろに箱をひったくった。そして、中の指輪を外すと左手の薬指にはめた。指輪はぴったりだった。
ジョナサンは呆然と私の行動を見ていた。
「ジョナサン・ガーベイ、これが私の答えよ」
ジョナサンの眼に光るものがあったように見えたのは私の見間違えだったのだろうか。
「ヤッホー!」
ジョナサンは、私を抱き上げるとクルクルクルクル踊るように回った。
「ジョナサン、目が回るわ。ジョナサンったら!」
私は軽く彼をこぶしでうちつけながらも、笑いが止まらなかった。
私の目に、体と一緒に飛び跳ねるジョナサンの栗色の髪が映った。私は思わずその髪にキスした。
幸せになれるはずだ。もう一度。きっと。
|
| (C) 2012 Paonyan?. All rights reserved |
|

