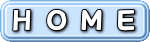


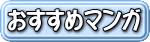





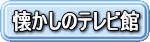
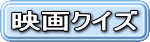
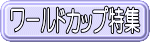





|
|
| ホワイト・クリスマスをもう一度 |
クリスマスの朝だった。カーテンを通して窓から差し込む光を浴びて、メアリーは眠りから覚めようとしていた。
朝だわ・・・光が・・・メアリーは徐々に目覚めつつある意識の中で考えていた。
光?メアリーは突然起きあがった。
陽が昇り、カーテンを通して薄い光が差している。その光をメアリーは感じるのではなく、はっきり見ていた。いや、光だけではない。カーテンも。
メアリーは思わず自分の目の前に手を差し出した。そう、自分の手。自分の手が見える!ブロンドの長い髪が、肩から下に流れている。昔のままの髪の毛。見える。
メアリーは隣に寝ているアダムの方を見た。漆黒の髪、端正な顔。おお、アダム。こんなにハンサムだったのね。
メアリーはよろよろと立ち上がって、カーテンをサッと開けた。薄い太陽の光に照らし出されて、降り積もった雪が白く光っていた。
これは何なの?夢なの?見えるわ。すべて見える。
「アダム」
メアリーは小さな声で呼びかけた。叫びだしたい気がしたが、叫ぶと夢から覚めるような気がしたのだ。
「アダム」
アダムは小さく伸びをして、目を開けた。
「やあ、おはようメアリー」
いつものようににっこり微笑んでから、アダムの顔は一瞬硬直した。
「メアリー?」
アダムは窓辺に佇むメアリーをジッと見つめた。それから、部屋の中を見回した。
「どうなっているんだ・・・。夢なんだろうか。メアリー、君が見えるんだ。君だけじゃない、すべてが」
アダムは呆然とつぶやいた。
メアリーはその瞬間喜びを爆発させてアダムに抱きついた。
「貴方もなのね!本当なのね。私たち、目が見えるようになったのよ!」
アダムはまだ呆然としていた。
「でも・・・そんなまさか・・・何故」
「でも、見えるわ。私は貴方が見えるの!」
「僕も君が見える。ああ、メアリー、君がこんなに綺麗だったなんて・・・」
アダムは飛び起きた。二人は抱き合い、笑いあい、涙をこぼしながら意味不明のダンスをしばし踊り続けた。
「ヘスター・スー!」
階段を降りると、メアリーはすぐにキッチンにいるへスター・スーに声をかけた。
へスター・スーはただごとならぬ声にびっくりしてすぐに出てきた。
「ヘスター・スー!」
メアリーはヘスター・スーに抱きついた。
「初めまして。ヘスター・スー!」
「まあまあ、どうしたの」
ヘスター・スーは面食らったように言った。
「奇跡よ!目が見えるの!見えるのよ。アダムも私も」
ヘスター・スーはすぐには意味が飲み込めないようだった。
「ほら、今日の貴方の服。黒いスカートに白いブラウス。ブラウスの襟には花模様が刺繍されているわ」
ヘスター・スーは驚いたように口を開いた。
「まあ・・・」
メアリーはそのまま踊るように外に飛び出した。
外は一面の銀世界だった。今は雪が止んでいて、薄い光が空から差し込んでいる。ホワイト・クリスマスを見るのは何年ぶりだろう。
雪ってこんなに白くて綺麗だったんだ。メアリーは、手で雪をすくった。
クリスマス休暇でそれぞれの自宅に帰っている盲学校の生徒たちのことが頭に浮かんだ。これが神が起こしたもうた奇跡なら、あの子たちにも視力が戻っているだろうか。そうだったら、どんなに良いだろう。
生徒のイーライがこの前言ったことが頭に蘇った。
「メアリー先生、雪って白いんでしょう」
「そうよ、イーライ」
「白ってどんな色なのかな」
イーライは生まれた時から目が見えなかった。メアリーは雪をすくってイーライの手の上に置いた。
「これが白よ。さあ、感じて」
イーライも今、初めて雪の白さをその目で見られているならどんなに良いか。
メアリーとアダムはほとんど駆けるようにして、道を歩いていた。チャールズがあとでクリスマスのお祝いを一緒に過ごすために迎えに来てくれることになっていたが、とても待っていられなかった。
「ほら、アダム。教会よ。そして、ここで勉強した学校でもあるわ」
メアリーは教会をアダムに指し示しながら言った。
「あの鐘よ。私たちがジョーンズおじさんと造った鐘」
アダムにとっては通り慣れた道でも勿論見るのは初めてだった。
オルソン商店の前では、掃除をしながらオルソンとガーベイが立ち話をしていた。オルソン夫人はガラスを磨いていた。
「こんにちは、オルソンさん、ガーベイさん」
メアリーは声をかけた。
「やあ、メアリー」
「こんにちは、オルソン夫人」
「あら、こんにちは、メアリー」
何気なく挨拶を交わしてからみんなハッとした。
「メアリー、私とオルソンは声でわかったんだよね」
ガーベイが聞いた。
「でも、家内がいるってどうしてわかったんだい?」
今度はオルソンが聞いた。
「ええ、ガラスを磨いていらしたのが見えたから」
「ええっ!?」
オルソン夫人が素っ頓狂な声を挙げた。
「初めましてって心境です。オルソンさん、ガーベイさんですね」
アダムがそれぞれに手を差し出して力のこもった握手をした。
「見えるのよ。私たち、目が見えるの」
オルソンとガーベイは顔を見合わせた。
「オルソン夫人、新しい茶色のドレス良く似合ってますわ」
メアリーが付け加えた。
「あら、どうもありがとう・・・」
そう言いながら、オルソン夫人はあんぐりと口を開けた。
「ひゃっほー!」
ガーベイが大きな声を出してメアリーを抱きしめた。
「奇跡だよ。クリスマスの奇跡だよ!」
ガーベイはアダムとメアリーを乗せて全速力で馬車を走らせた。嬉しくて仕方がないという顔だった。
インガルス家ではちょうどチャールズが納屋から出てきたところだった。
ガーベイが馬車を止めると、チャールズはすぐにメアリーに手を貸そうと近寄った。
「何だ。ガーベイに送ってもらったのかい。もうすぐ迎えに行こうと思ってたんだよ」
「父さん!」
メアリーはチャールズにいきなり抱きついた。
「私の昔のクリスマスプレゼントのシャツ、まだ大事にしてくれていたのね」
チャールズは一瞬凍り付いた。彼が着ていたのは、昔メアリーがクリスマスに贈ってくれた青いシャツだった。
大事な時しか着ないように取ってあったもので、クリスマスの今日は着るのにふさわしいと思って出してきたものだった。
「そうだが・・・。どうして、わかったのかな。匂いでもついているのかな」
チャールズはとまどったように、メアリーを見て、それからガーベイを見た。
「匂いだって、チャールズ」
ガーベイが白い歯を見せて笑った。
「見えるのよ。父さん、私見えるの。アダムもよ。視力が戻ったの」
チャールズは信じられないという表情でメアリーを見た。
「でも・・・そんなことは・・・勿論本当なら素晴らしいんだが」
「本当ですよ」
アダムは一人で身軽に馬車から飛び降りた。
「これが家なんですね」
アダムは家を見つめた。
「すてきだ。暖かそうな家だ」
キャロラインが外の気配を聞きつけて出てきた。
「いらっしゃい。早かったのね」
メアリーはまっすぐにキャロラインの腕に飛び込んだ。あまりの素早さにキャロラインは面食らっていた。
「母さん・・・」
メアリーの頬を涙が伝い落ちた。
「まあ、どうしたの。メアリー」
キャロラインは心配そうにメアリーの顔を見つめた。
「見えるって言うんだ」
チャールズが呆然と言った。
キャロラインはチャールズを見、それからもう一度メアリーを見た。
「母さん、見えるの。見えるのよ。本当に・・・」
キャロラインは嗚咽をこらえるように口に手を当てて囁くように言った。
「ああ、神様」
キャロラインとメアリーはしっかりと抱き合った。
「すごいよ。素晴らしいよ!」
チャールズがアダムを乱暴にかき抱いた。ガーベイが大きな声で「ブラボー!」と叫んだ。
その日のクリスマスは最高の幸せだった。メアリーは懐かしい家の中をもう一度見ることの出来る喜びに浸り、
チャールズとキャロラインはそんなメアリーを見る喜びに浸った。アダムにとっては、話慣れた家族なのに初めて
顔を見る不思議な感覚が残っていたが、喜びの大きさはすぐにその違和感を吹き飛ばした。
キャロラインのご馳走をみんなでたらふく食べ、プレゼントを交換した。
「もうこのカードはいらないわね」
ローラが点字で打ったクリスマスカードを示した。
「いいえ」
メアリーはそのカードを受け取って開いた。
「大好きな姉さんへ、メリー・クリスマス」
メアリーはカードを読むとローラと抱き合った。
「目が見えるようになってもこれは大事な宝物。今までのものと一緒に大事に取っておくわ」
その後はチャールズのバイオリンに合わせて、歌い踊った。こんなに楽しいクリスマスは一家にとって
何年ぶりだったろう。
その夜はメアリーとアダムはインガルス家に泊まることになった。
姉妹のたっての希望で、メアリーとローラは昔一緒に使っていたベッドで寝て、アダムはカーテンの向こうで
アルバートと一緒に寝ることになった。
「狭くなって悪いね、アルバート」
アダムが言った。
「全然かまわないよ。でも、ローラのいびきだけは覚悟した方がいいよ」
アルバートが真面目な顔をして言った。
「凄く久しぶりね、姉さんとこうやって一緒に寝るの」
ローラが床の中で言った。
「そうね」
「前は寝ながら色々と話したわ。男の子のこととか」
メアリーがクスリと笑った。
「姉さんはすごくモテたものね」
「アダムに聞こえるわ」
メアリーが小さな声で囁いた。
「今気になるのはアルマンゾのこと?」
メアリーが言った。ローラは少し赤くなった。
「でも、向こうは気にしてないもの」
「そうね。今はね。でも、待つの」
メアリーはローラの方を向いて言った。
「ローラはどんどん花開いている。いつか完全に花開いた時、アルマンゾの方から寄ってくるわ」
「本当にそう思う?」
ローラが目をキラキラさせて聞いた。
「思うわ。だって、貴女は私の妹ですもの。その魅力に気がつかない男性なんて、こちらから願い下げた方がいいわ」
二人は声を合わせて笑った。
今晩は特別にチャールズが子守歌代わりにバイオリンを弾き続けてくれている。
暖かい家、愛する家族に囲まれて、メアリーは心からの幸せを感じながら、程良くやってきた眠気に身をゆだねた。
「メアリー」
アダムの声が聞こえた。
「メリー・クリスマス、メアリー」
アダムのキスを頬に感じた。
カーテンが開かれる音がした。
「さあ、父さんが迎えに来てくれる前に支度しないとね」
メアリーはゆっくり身を起こしてアダムの声のする方を見た。
「メアリー?起きた?」
「ええ、アダム。おはよう」
メアリーは静かに言った。
「今日はホワイト・クリスマスだってヘスター・スーが言っていたよ」
「降っているの?」
「いや、今は降っていないらしいが積もっているって」
メアリーはガウンを羽織って、アダムの声のする窓辺に行った。
アダムはメアリーの肩を抱いた。
「メリー・クリスマス、アダム。今日はホワイト・クリスマスなのね」
「そうだね。ニューヨークでも良くクリスマスには雪が積もったよ。きれいだった。そして、空から雪が舞い落ちてくる瞬間がまた素敵なんだよね」
アダムは小さなため息をついて言葉を切った。
「もう一度見たかったね。ホワイト・クリスマスを」
メアリーはアダムの手をギュッと握った。
「そうね。本当にそう・・・。でも、アダム、私たちホワイト・クリスマスを知っているわ。覚えているわ。雪の白さを今でも思い描ける。それだけでも幸せよね」
アダムはメアリーを抱きしめた。
「そうだね。その通りだ」
メアリーの頬を涙が一筋伝い落ちた。
|
| (C) 2012 Paonyan?. All rights reserved |
|

